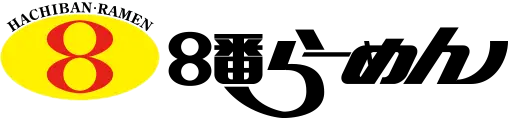
テイクアウト電話注文を削減。北陸で100店舗超展開「8番らーめん」の地方チェーンだからこそのDX戦略

-
導入の背景
ピークタイムの電話注文を削減するためにテイクアウトネット注文を導入
-
導入の効果
店舗への電話件数が明らかに減少し、お客様にとっても店舗にとっても利便性が向上した。また、POSシステムとの連携により注文の二度打ちが不要になり、注文の見逃しや入力ミスを解消できた
株式会社ハチバンは「『食』と『おもてなしの心』で人やまちを笑顔に、元気に。」を経営理念に、国内では北陸地域を中心として132店舗・海外でも165店舗の店舗を展開するフランチャイズチェーン企業です。(2024年3月20日現在)
ハチバンの主力業態である「8番らーめん」は、昭和42年(1967年)に国道8号線沿いで第1号店をオープンしました。以来、主力メニューである「野菜らーめん」を中心に、創業当初からのこだわりの味を守り続け、地域の方々に愛される存在となっています。
同社での8番らーめん業態では、2023年より公式ネット注文「8番テイクアウト」のサービスにCamelシリーズのCamel Orderを活用。テイクアウトの事前注文受付予約により、お客様の利便性向上・店舗のオペレーション効率化を進めています。
ハチバンの取締役 執行役員 8番らーめん事業部長の後藤様に、ハチバンでのCamel Orderの活用背景・今後のDX戦略についてお話を伺いました。
コロナ前より取り組んでいた8番らーめんのテイクアウト・デリバリー・ドライブスルー事業
8番らーめんではかなり昔からテイクアウト・ドライブスルーに取り組まれていたとお伺いしています
当社では約15年前からドライブスルーでのラーメン販売を行っており、コロナ禍をきっかけにテイクアウトを開始したわけではありません。もともと、他社のファーストフードチェーンがドライブスルーを提供しているのを見て、北陸は車社会であることから、ラーメンでも実現可能なのではないかと考えたのが始まりです。
その後、「電話で予約できればより便利になるのではないか」という発想から、店頭でのテイクアウトにも対応するようになり、徐々にサービスを拡充してきました。
また、ご年配のご両親が「自宅で8番らーめんを食べたい」と購入されるケースや、小さなお子様のいるご家庭では「店内では子どもが動き回るため、自宅で落ち着いて食事をしたい」といったニーズにも対応しています。
さらに、北陸地方は降雪が多く、大雪の翌日などには売上が伸びる傾向があります。これは、長年にわたり、寒い時期に気軽に利用できる「自炊の代替手段」として親しまれてきたことが要因の一つであると考えています。
フードデリバリーへの取り組みのきっかけは?
コロナ禍をきっかけに、ドライブスルーやテイクアウトに加え、フードデリバリーの導入も検討することとなりました。現在は、Uber Eatsや出前館などのデリバリーサービスを活用しています。
北陸地方は首都圏のように店舗が密集しているわけではないため、「この地域でフードデリバリーの需要があるのだろうか」と懸念していました。しかし、特に繁華街エリアでは一定のニーズがあり、サービスを開始してから予想以上の反響があったことに驚いています。
コロナを経てテイクアウト・デリバリーの売上比率が5%から15%へ
コロナ禍を経て、テイクアウトやデリバリーの文化が社会に広く定着したと実感しています。コロナ以前は、店舗全体の売上に占めるテイクアウト・デリバリーの割合は約5%でしたが、コロナ禍を経て大幅に成長し、現在では全体の15%を占めるようになっています。この傾向はアフターコロナにおいても継続しています。
特に地方だからこそ、繁華街で夜遅くまで外食をするよりも、自宅で食事をとるケースが増えていると感じています。
Camel Order導入後の効果、店舗様の反応
ピークタイムの電話注文を削減するためにテイクアウトネット注文を導入
コロナの影響でテイクアウト需要が増加したことに伴い、電話でのテイクアウト予約も大幅に増加しました。しかし、正午などの店舗のピークタイムには業務が立て込んでおり、電話に対応できない状況が発生していました。
特に混雑する時間帯には、1時間から1時間半にわたって電話に出られないこともあり、お客様が何度かけても繋がらず、不満の声が寄せられるケースが増えていました。こうした課題に対応し、お客様の利便性を向上させるとともに、店舗の負担を軽減するため、テイクアウトのネット注文を導入することを決定しました。
他社サービスとも比較していたと聞きますが、Camel Order導入の決め手を教えてください
当初は他社のサービスを利用していましたが、そのサービスが終了することになり、新たな選択肢を検討していた際にCamel Orderと出会いました。
当時は3社ほどのサービスを比較していましたが、特に提案のスピード感、大手POSレジとの連携性の高さ、および豊富な連携実績が導入の決め手となりました。以前利用していたサービスはPOSレジと連携していなかったため、注文が入るたびに店舗のPOSやハンディ端末に手作業で入力する必要があり、オペレーション負担が大きいという課題がありました。しかし、Camel OrderではPOSと自動連携が可能で、厨房のキッチンプリンターから調理伝票を自動で出力することができます。
この機能は比較検討した他社のサービスには実装されていなかったため、Camel Orderの導入をすぐに決めました。
Camel Order導入後の具体的な効果について教えてください
Camel Orderを導入したことで、店舗への電話件数が明らかに減少しました。これは、お客様にとっても店舗にとっても利便性が向上した結果であると実感しています。特に、ピークタイムに店舗スタッフが電話対応をする必要がなくなった点については、スタッフからも高く評価されています。
さらに、POSシステムとの連携により、注文の二度打ちが不要になったことも大きな効果の一つです。従来は、注文の見逃しや入力ミスが定期的に発生していましたが、POS連携機能の導入によって、こうした問題を解消することができました。
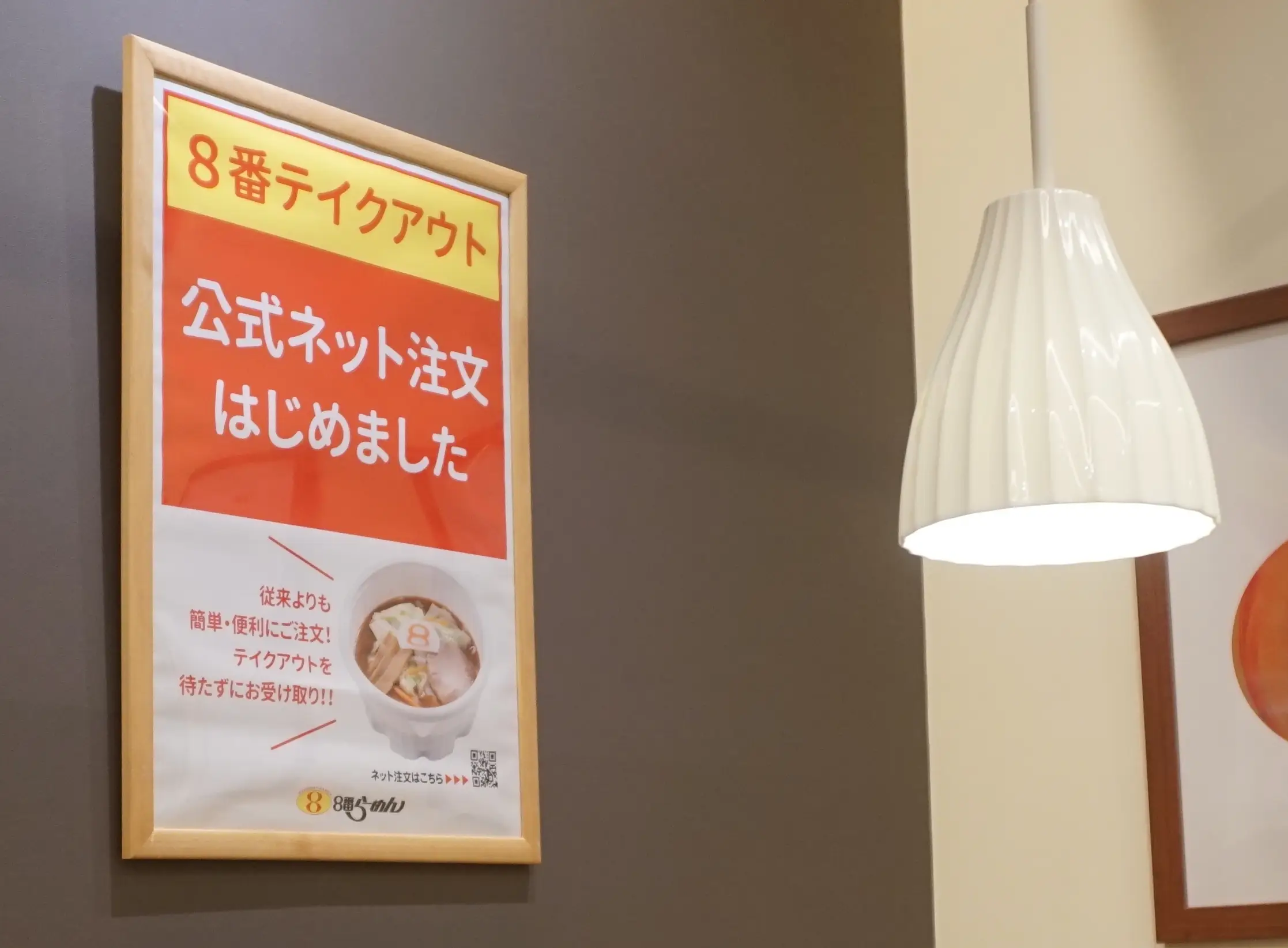
DXへの取り組み・今後の展望について
Camel Orderでの公式ネット注文の立ち上げだけでなく、色々な面でDXに力を入れられているようにお見受けします
首都圏では人材を確保しやすく、DX(デジタルトランスフォーメーション)の導入も進んでいますが、地方では人口減少や人手不足が深刻な課題となっています。特に、8番らーめんが広く展開している石川・福井・富山といった地域では、人手不足の影響が顕著です。しかし、当社は50年、60年と地域に根ざして店舗を運営してきたため、地元コミュニティとのつながりを大切にしています。そのため、「人手が足りないから」といった理由だけで簡単に店舗を閉鎖することはできません。
こうした状況の中で、「人手が不足している部分は機械に任せ、人が行うべき業務は人が担う」という方針のもと、ここ数年で本格的にDXを推進しています。DXの導入は単に利益を追求するためではなく、業務の効率化によって生まれた余剰リソースを、お客様へのサービス向上に充てるという考え方です。利益を目的としたDXではなく、むしろ生まれた余力を現場のスタッフに還元することが重要だと考えています。
具体的には、タブレットオーダーシステムや配膳ロボット、公式アプリなどを導入しています。しかし、これらの導入によって接客を完全になくすわけではありません。例えば、タブレットオーダーを導入している店舗においても、お客様が注文に迷われている際には、スタッフが声をかけ、適切にフォローを行っています。
タブレットオーダーの導入によって接客がゼロになるわけではなく、むしろスタッフの負担を軽減し、空いた時間を活用して、より質の高いサービスを提供できる体制を整えることが可能になりました。
今後のDX戦略に関して御社の展望や、その中でのCamelシリーズへの期待があれば教えてください
今後も、店舗の人手不足をどのように解決していくかという視点を軸に、デジタル技術の活用を進めていきたいと考えています。
tacoms社からは、Camelシリーズの製品ロードマップや新製品についてお話を伺っていますが、今後も人手不足の解消に貢献する新製品がリリースされる予定とのことで、大いに期待しています。また、tacoms社の開発スピードの速さを実感しており、今後もさまざまな挑戦を予定していることを聞いているため、今後のtacoms社の取り組みに大きな期待を寄せています。
Camel導入についてのご相談や
無料デモのお申し込み・
資料請求について
お気軽にお問い合わせください。

